トップ > 医療関係者・学生の皆様 > 先輩からのメッセージ
先輩からのメッセージ
先輩からのメッセージ 三好 潤 先生
2019年4月より杏林大学第三内科学教室・消化器内科学内講師を拝命しました三好潤と申します。3月までは米国シカゴにあるThe University of Chicago, Department of Medicine, Section of Gastroenterology, Hepatology, and Nutrition(シカゴ大学消化器科)にてPostdoctoral Scholar(ポスドク、博士研究員)として腸管微生物叢(microbiota)の研究に携わっていました。今回、米国での研究生活についてご紹介するというテーマをいただきましたので、自己紹介を兼ね、お話しさせていただきたいと思います。
(1)ポスドク生活が始まるまで(I)―臨床医がアメリカで基礎研究を始めるきっかけ
炎症性腸疾患(IBD)については、まだ分からないことがたくさんあります。多くの臨床的課題に対して臨床研究による新たなエビデンスの構築が必要です。一方、IBDの現在の治療ゴールは寛解の導入・維持ですが、「治癒」を目指すためには病態生理を解明するための基礎研究が不可欠です。私は、IBDを専門とするため臨床・基礎の両立を目指したいと考え、臨床の研鑽を積むとともに、大学院に進学しました。指導者に恵まれ、日々の臨床は充実し、臨床研究、基礎研究を行う機会も得ました。私にとって、実地臨床は「目の前の」患者さんのため、臨床研究は「近い将来の」患者さんのため、基礎研究は「未来の」患者さんのため、という思いでした。一方で、多くの患者さんに会う中で、「IBDの根本治療を目指して挑戦したい」という気持ちが次第に強くなりました。そして、「基礎研究をするからには最先端を学びたい。これからの研究生活の基盤となるようにしっかりと勉強したい。」と考え、IBD研究が盛んなアメリカへの留学を希望するようになりました。そして、日比紀文先生(現・北里大学北里研究所病院炎症性腸疾患先進治療センター長)のご助力をいただき、2014年10月よりシカゴ大学消化器科でポスドクとなりました。日比先生には、この場を借りて、あらためてお礼申し上げます。
(2)ポスドク生活が始まるまで(II)―初めてのアメリカ暮らしでの驚き
いざ渡米すると、「電話で英会話」という壁に直面しました。インターネット、電気などを頼む際に、最初はどうしても電話になります。相手の顔が見えず、ジェスチャーに訴えることもできない、という状況は、通常の会話よりもハードルが高かったです(今でも)。メール、オンライン処理は、本当にありがたかったです。ネットが普及する前に留学された先生方は、よほど苦労されたのではないでしょうか。さらなるトラップは「カタカナになっているのにアメリカ英語で全く違う単語」です。相手の推察力のおかげでカタカナ発音でも文脈とアクセント次第で通じることが多いのですが、全くダメというものもあります。例えば、家具を買った「イケア」は「アイキア」でした。車の「ウィンカー」は「ブリンカー」です。日常生活ではないですが、「ナトリウム」、「カリウム」は基本的に「ソジウム」と「ポタシウム」。有機溶剤の「キシレン(xylene)」に至っては「ザイリーン」と強力そうで個人的には好きでした。また日常生活での単位は複雑でなぜこんなことになっているのか分かりません。長さは、「マイル」「フィート」「インチ」、液体は「ガロン」「オンス」、重さは「ポンド」「オンス」、温度は「℉(華氏)」を使用します。一方で、研究室内は、「メートル」、「リットル」、「キログラム」、「℃」です。アメリカ人の同僚も換算が分からなくなると言っていました。もしアメリカ旅行中に天気予報で「32 degree」と言っていたら、「32℉ = 0℃」なので寒いです。気をつけてください。また大陸性の気候なのか(?)、気温の変化や天気の移り変わりが激しい印象があります。ある日の夏の嵐の風景は映画のようで格好良かったです。もう少し内陸ではトルネードの季節でもあります。

自宅からみた夏の嵐
ミシガン湖の奥に見えるダウンタウンは大雨です。この後、こちらも雨になりました。
(3)シカゴ大学での研究生活(I)―実験見習いからオリジナル研究の立ち上げ
さて、シカゴでの日常生活だけでもお話ししたいことはたくさんあるのですが、研究のための渡米でしたので、本題の研究生活についてお話ししたいと思います。シカゴ大学消化器科は全米でも屈指のIBDセンターを有し、所属したEugene B. Chang研究室はmicrobiota研究で世界をリードする研究室の一つです(写真2)。研究室のボス(principal investigator; PI)であるChang教授は穏やかな性格で長年の研究生活で培ったネットワークと眼力は皆が一目を置く先生でした。Chang先生の指導を受けることができたのは本当に幸運でした。大学院修了後から研究のブランクがあり、最初は他のポスドクの手伝いをしながら実験手技を学ぶところから始めました。その後、与えられたテーマでの研究も開始しましたが、よりIBD臨床に関連するプロジェクトを自分自身で立ち上げたいと考え、文献にあたりながら企画書を作り続けました。そして、そのプロジェクトが、その後の私のメインテーマにつながりました。何事も諦めないことが肝心だと学びました。また臨床で必要な論理的思考は基礎研究でも通用すると感じましたし、逆もそうだと思います。そして、しっかり頑張れば見る人は見てくれているというのは世界共通なのだろうと思いました。結局、シカゴ大学では4年半を過ごすことになりました。

Chang研究室の休憩エリアからみたダウンタウン
手前は大学のグラウンドです。良い眺めで癒されます。
私が始めた研究テーマは、妊娠中の母体や小児期の抗菌薬使用と児のIBD発症リスクの増加が関連しているという近年の疫学的知見から発想を得たものです。IBDの病態生理として遺伝的背景や環境因子をもとに生じる免疫異常が想定されていますが、特に、近年の全世界的な著しい罹患率の増加は環境因子の関与が強く疑われています。そして、IBDに関与する環境因子の変化として、食事内容や衛生環境などさまざまな要因が指摘されていますが、特に腸管微生物叢(microbiota、マイクロバイオータ)が大きな役割を果たしていると考えられています。上記の疫学的知見は、出生後早期の腸管microbiotaの乱れ(dysbiosis、ディスバイオシス)が児の成長後のIBD発症につながることを示唆していますが、ヒト疫学研究の限界として、この点について、因果関係、機序を明らかにすることはできません。そこで、私たちは、この疫学的知見を再現するIBDマウスモデルを確立し、周産期の抗菌薬投与により母体に生じたdysbiosisが仔に垂直伝播し、免疫異常を生じること、さらに腸炎発症リスクが上昇することを明らかにしました。もちろん周産期の抗菌薬投与が全て悪だと言うつもりはありません。適切な抗菌薬使用はきわめて重要です。一方で、私たちの研究結果はIBDの病態生理における周産期の腸管microbiotaの重要性を示唆しています。このマウスモデルを用いた研究は今もシカゴ大学と継続しています。臨床に還元できるようなトランスレーショナルリサーチをこれからも行っていきたいと考えています。
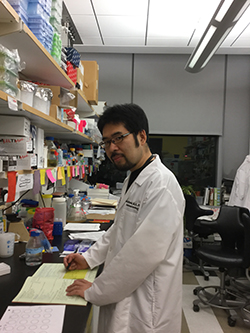
研究室内での一風景
ヒゲを生やしていた頃です。このあと、もみあげまでつながっていきます(笑)。
(4)アメリカの研究キャリア―競争、競争また競争
私も渡米するまで全く知りませんでしたが、アメリカの研究者のキャリアシステムも興味深いものがあります。私がシカゴ大学で見聞した限りではありますが、ご紹介したいと思います。まずポスドクは、Ph.D.(またはM.D.)の学位を取得した駆け出しの研究者が付くポジションです。ここで4−5年間(分野によります)の研究活動に従事し、実績を積み、研究のネットワークを作り、研究室運営のノウハウも学びます。そして、大学等のアカデミア志望の若手はAssistant Professorを目指します。Assistant Professorになると独立して自分の研究室を持ちます。また、企業に所属する研究者を目指す者もいます。人事の流動性もあり、日本よりも産学の垣根が低いように感じました。このような修行中の身のポスドクですが、基本的に1年毎の契約更新です。本人の実績が足りない、研究室の予算が足りない、等の事情によっては更新してもらえません。研究室の予算というのはきわめて切実な問題です。研究室のボスの研究費(グラント)が尽きてしまうと…その研究室は消滅します。一方、研究者の入り口に立つまでにも激しい競争があります。例えば、研究室に所属する博士課程の大学院生については、PIが学費に加え、給料(生活費)まで支払うので、学生はアルバイト等の心配がいりません。しかし、逆に言うと、Ph.D.コースに入学が許可されるのは、NIHのグラントをすでに獲得しているか、その見込みが十分にあるような学生達です。さらに、メディカルスクールは通常4年間でM.D.取得を目指しますが、各大学に7年間のM.D./Ph.D.コースというものがあります。このコースに入ると、7年間の学費(シカゴ大学だと年間1千万円くらいという噂でした)が全額無料で、かつ生活費まで出ます。卒業後は臨床メインで行くのも研究メインで行くのも自由です。入学は大激戦だということです。さて、めでたくPh.D.を取得すると、さらなる競争が待っています。まずポスドクの座を競いますが、そこには私のような外国人研究者も多く参戦します、PIのポストはさらに限られます…。このように、どこまでも競争社会な仕組みです。ただ、ポジションを取れば待遇は良くなります。研究費も大型のものがあります。大きな業績を上げれば、安定したポジションにつけます。桁違いの寄付金が来ることもあります(私がいる間にもシカゴ大学Microbiomeセンターに約100億円を寄付した家族がいらっしゃいました)。ちょっと極端かもしれません。
私は、M.D./Ph.D.コースへの投資を見て、臨床が分かる研究者(physician scientist)を科学技術に関する国家戦略として重要な要素と捉えているのだろうと感じました。あくまで私の印象ですが、M.D.とPh.D.は、やはり目の付け所が違います。両者の橋渡しをできるphysician scientistは、大きなシナジー効果を生み出すポテンシャルがあるのではないでしょうか。その点、日本の、勉強したいと思う臨床医が大学院博士課程に進学できる仕組み、論文博士を得るために研究に携わる仕組みは、すごい人材を生み出す力があるのではないかと思います。臨床も研究も、というのは大変なことは間違いないのですが(もっと公的なサポート等も充実していると良いのですが)、特に若い先生方には、ご自身の大きな可能性を信じてチャレンジして欲しいと考えていますし、そのお手伝いができればと思います。
(5)シカゴ大学での研究生活(II)―とは言え、息抜きも必要です
さて、研究内容、キャリアなどの堅い話が続きましたが、研究者も人間です。息抜きが必要ですし、同僚は皆、メリハリをつけて仕事をすることが上手でした。そして研究室の仲間は各自の研究で忙しくしながらも、お互いに助け合い、チームとしての一体感がありました。研究室では、毎月の合同誕生日会、クリスマス・ニューイヤーパーティー、ベイビーシャワーなどのイベントを行い、また近所のバーを「セカンド・オフィス」と呼び、たびたび若手会をしていました。どこの組織にでも、そういう企画、仕切りが上手な人がいるものだなと変なところで感心していました。ありがたいことです。また、シカゴとその周辺の季節の移り変わりはとても綺麗ですし、家族でいろいろとドライブ旅行に行ったのも良い思い出です(写真4)。ただ、シカゴの冬は厳しいです(写真5)。

夏のスリーピング・ベア・デューンズ
ミシガン湖の砂丘の中でも、このSleeping Bear Dunes(ミシガン州)は特に有名です。

自宅からみた冬のミシガン湖
1-2月になると流氷が押し寄せ、湖が凍ります。
気温を見るときに風なども考慮した体感温度に注意しなくてはならないと学びました。滞在中一番寒い日は体感気温で-50℃近くになり、2日間ほど休校になりました。2019年3月に帰国する際には、同時期に帰国する上海から来ていた研究者と合同で盛大な送別会を開いてもらいました。

送別会
Chang研究室の皆と集合写真です。大変お世話になりました。
(6)最後に―これからが本当の始まりです
最後まで読んでいただきありがとうございます。私個人の意見、体験に基づく話ではありますが、皆様が研究や海外留学に関心を持つきっかけとなれば幸いです。結局のところ、日本とアメリカで表現の違いはありますが、根は同じだと思います。きちんと考える、他人を尊重する、ベストを尽くす、それだけです。4年半のシカゴ生活は、研究者としての下地をつくる期間でした。当時の仲間もアメリカ各地で研究室を持って動き始めています。彼らと共同研究を立ち上げていくのが楽しみです。杏林大学医学部第三内科学教室消化器内科の一員として、「クリニカルクエスチョンに基づくリサーチ」をモットーに、これからが本当の始まりだと思っています。研究内容など、ご興味のある方は、是非お声かけください。意気込みだけは大きく申しましても、まだまだ経験の浅い若輩者でございます。今後とも、皆様のご指導、ご鞭撻のほどよろしくお願い申し上げます。
→OBの先輩からのメッセージ Vol.001「やまぐち内科眼科クリニック 山口康晴先生」
→OBの先輩からのメッセージ Vol.002「聖路加国際病院 中村健二先生」


